M&A件数は年々増加の傾向にあります。
日本の経済的な背景から中小企業の倒産率が高くなっており、その出口としてM&Aが採用されることも。ですが、M&Aは買い手は見つけやすいものの、売り手の開拓で頭を抱える仲介会社が多いです。
そこで今回は「売り手開拓におけるM&Aの営業方法」をM&Aアドバイザリー経験があり会社を経営している私が徹底解説します。
本記事では、売り手開拓におけるM&A営業のコツまで解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
\ M&Aの売り手・買い手開拓はお任せ /

M&Aの営業方法
まずは結論から。売り手開拓におけるM&Aの営業方法をまとめると以下の通りです。
順番に見ていきましょう。
M&A営業方法①:テレアポ
まずは王道のテレアポです。
M&A仲介会社の多くは、新卒に1ヵ月当たりのアポ数ノルマを設けて、1日中大量にテレアポをさせることが多いです。その過程でM&Aの内容を理解させ、突出した成果を出す社員に役職を付ける流れがスタンダードですね。
ただ、むやみにテレアポをすることは、レピュテーションリスクに繋がります。実際、「会社名+迷惑電話」という検索ボリュームがかなり膨らんでる会社さんも多いです。信用が大切なM&Aにおいて、営業で信用を損なうのは本末転倒。
特に営業代行の会社に外注すると、クレーム発生のリスクが倍増します。そもそもビジネスモデルや財務が複雑に絡むM&Aにおいて、再委託がデフォルトの営業代行サービスは相性が最悪です。
なので、M&A営業をテレアポで実施する際には、ただの迷惑電話にならぬよう自社人員にて丁寧に行うことを心がけましょう。
M&A営業方法②:飛び込み
M&A営業方法2つ目は飛び込み。
インターネット黎明期以前の営業手法ですが、現在でも飛び込み営業を実施している会社は多数あります。ただ、1件当たりの所要時間が長くなりやすく効率は悪めです。
加えて、近年ではオフィスを持たない会社やセキュリティが強いオフィスビルも多いため、そもそも飛び込みすらさせてもらえないケースがあります。
なので、仮に飛び込み営業をするのであれば、あくまでファーストコンタクトを別手法で獲った後に、アポイントをしっかり取る形で実施するのが良いでしょう。
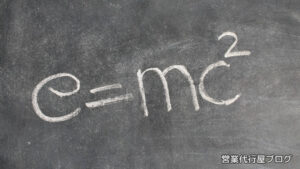
M&A営業方法③:リファラル
M&A営業方法3つ目はリファラルです。
要するに、知り合いの経営者等から紹介を受ける方法です。M&A仲介会社の営業課題は基本的に売り手開拓なので、知り合い経営者から会社売却(もしくは事業譲渡)したい人はいないかを探っていく感じです。
既存の人脈から探していく方法もありますし、銀行や税理士、弁護士など経営者の知り合いが多い業態の知人経由で紹介してもらうよう動く方法もあります。
M&A営業方法④:ペイド広告
M&A営業方法4つ目はペイド広告。
検索エンジン上で実施するリスティング広告やSNS広告など。検索キーワードやペルソナを設定し、クリック型課金の形式で広告を打つことが基本です。
資金力があれば集客が確実に行えるメリットがある一方で、どういったキーワードでどのようなペルソナを集客するのか?LPは最適化されているか?など、カスタマージャーニー全体を調整していく必要は当然あります。
加えて、資金力がないと継続は難しいです。直近では、CPCが爆上がりする現象も多方面で見られており、CPAが合わない現象が多発しています。ペイド広告だけに依存するリスクもあると認識しておきましょう。
M&A営業方法⑤:オウンドメディア
次の営業方法はオウンドメディアです。
メディア経由でインバウンドリードを獲得する方法ですね。想定リードが検索しそうなキーワードでSEO対策を行う形式です。
テレアポなどのアウトバウンド手法と異なり、一度メディアやコンテンツを作成すると、半継続的にリードの自動獲得が可能。資産性が生まれるため、多くの企業が積極的に採用している手法です。
しかし、SEO対策の難易度は年々上がっており、SEOの専門会社に委託しても成果が全くでないケースが多々あります。SEOは重要なデジタルマーケティングの手法ですが、中小企業ほど後回しになっている現状がありますね。
ちなみに弊社では、SEOのご依頼も受けております。現役のアフィリエイターが再委託なしでSEO対策を行うため、いわゆる机上の空論コンサルタントではありません。興味のある方は下記よりHPをご覧くださいませ。
M&A営業方法⑥:メール・フォーム
5つ目はメール・フォーム営業です。
見込みリードをリスト化した上で、メールやお問い合わせフォーム経由で営業する方法です。テレアポのような営業工数が発生しない一方で、返信率や商談化率が低くなりやすいデメリットがあります。
AIを活用したメールやお問い合わせフォームの大量営業ツールもありますが、AIツールをブロッキングする機能を噛ませている企業も多いので、意外と効率良く営業することは難しいのが現状です(現状のAIツールやRPAツールでは、認証機能を突破できない)。
ちなみに弊社では、メール・お問い合わせフォーム営業をメイン手法としています。リスト精査や営業文面、営業タイミングなどを最適化することで、レピュテーションリスクを下げつつ商談化率2-3%を実現しています(M&A業界だと、最大で商談化率30%まで引き上げたこともあります)。
M&A営業方法⑦:SNS(XやFacebook)
M&A営業方法7つ目はSNSです。
M&Aは初期段階でトップ面談が必要なこともあり、経営者層が運用している率が高いX(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを活用することが主流です(他にもYouTubeも人気)。
基本的にはM&Aに関するSNS運用を行い、M&Aに興味のある経営者をフォロワーに付けていき、そこからウェビナーや発信を通してリード化、クロージングまで持っていく流れです。
ただ、SNS運用をする経営者は集客を目的としているケースが大半。要するに、自社商品を売る販路としてSNSを見ているので、そこにM&Aの話を持ち掛けても成約率は落ちやすい傾向にあります。
なので、インバウンドリードを得る算段なのであれば、オウンドメディアの方が確度は高いと言えるでしょう。とはいえ、集客の難易度は低くなるので、挑戦してみるのはおすすめです。
M&A営業のコツ!M&A営業に必要なことは3つ
次に、売り手開拓におけるM&A営業のコツを3つに厳選して解説していきますね。
順番に見ていきましょう。
M&A営業のコツ①:リスト選定を徹底する
まずリスト選定の徹底です。
売り手開拓をするのであれば、そもそも会社売却や事業売却を想定している会社に営業をする必要があります。順調にグロースアップしている会社にM&Aの交渉を持ちかけることも可能ですが、成約率はガクっと落ちてしまいますので。
なので、着手しているビジネスモデルを整理し、どこでキャッシュを得ているのか?資金繰りはどうなのか?マーケット的に将来性はあるのか?など、様々な要素から売り手としての角度を計算していきます。
仮に会社に売却意思が薄かったとしても、売却した際の評価額が高くなりやすいことや、スイングバイIPOの可能性を示唆できるのであれば、成約率はグンと上がりますからね。
東京商工リサーチ等でリストを購入して、とりあえず営業ローラー作戦に出る方法もありますが、大手BIG4ならまだしも中小企業によるM&A仲介だと、資金的にも人的リソース的にも効率が悪くなるので、あまりおすすめはしません。
M&A営業のコツ②:決裁者までの壁を認識する
一般の営業でも決済者にコンタクトを取ることは非常に重要です。
しかし、M&Aにおける決済者は基本的に代表取締役です。なので、一般の営業よりも決済者までの壁が多いことがあります。
まずは電話やメールを処理している外注部隊がおり、その後に管轄社員、上長、マネージャー、役員、と様々な登場人物が推測されます。それぞれどうすり抜けて代表取締役まで辿り着くかを考えておかないといけません。
テレアポでいきなり「社長はいますか?」などと攻めるのは愚の骨頂の極み。レピュテーションリスクしかありません。二度と関係は持ってもらえないでしょう。
決裁者を抜けていく方法は多岐に渡りますが、どれも価値あるクローズドの情報なので、ここでは公開いたしません(クライアント様には公開しております)。
M&A営業のコツ③:ビジネスの上座から理解する
最後は、上座から理解すること。
M&Aは会社経営におけるすべてを網羅的に理解していないと話が成り立ちません。当たり前ですが、ビジネスモデルが理解できない、財務諸表が読めない、会計知識がない、法務リテラシーがゼロ、会社法や民法の理解がないような人材では取り扱いが難しいです。
厳密には取り扱いはできますが、秘書業務の範囲で終わり。なので、自分から新規顧客を掴んでくることはできず、見込みリードとコミュニケーションを取り、信頼値を得ていく業務に従事するしかない人材が大半です。
M&Aにおける新規リード獲得をするのであれば、ビジネスの上座から下座までの理解は必須。M&A営業のコツというよりも最低条件と言えるでしょう。
ちなみに、弊社運営の営業代行屋では、M&Aアドバイザリー経験者である経営者人材が一気通貫で営業を代行しています。成果報酬制で固定費用も発生しないので、M&Aにおける売り手開拓にお困りの方はお気軽にご相談ください。
M&Aの営業方法:まとめ
M&Aの営業方法は上記の通り。
様々な営業手法がありますが、会社ごとに最適な営業手法は変わりますので、自社のリソースに合わせて、やり方を選ぶと良いでしょう。
もし「営業リソースが足りない」「営業しているものの上手くいかない」という場合は、ぜひ弊社までお問い合わせください。営業代行や営業コンサルティング(内製化支援)を実施しております。
\ M&Aの売り手・買い手開拓はお任せ /


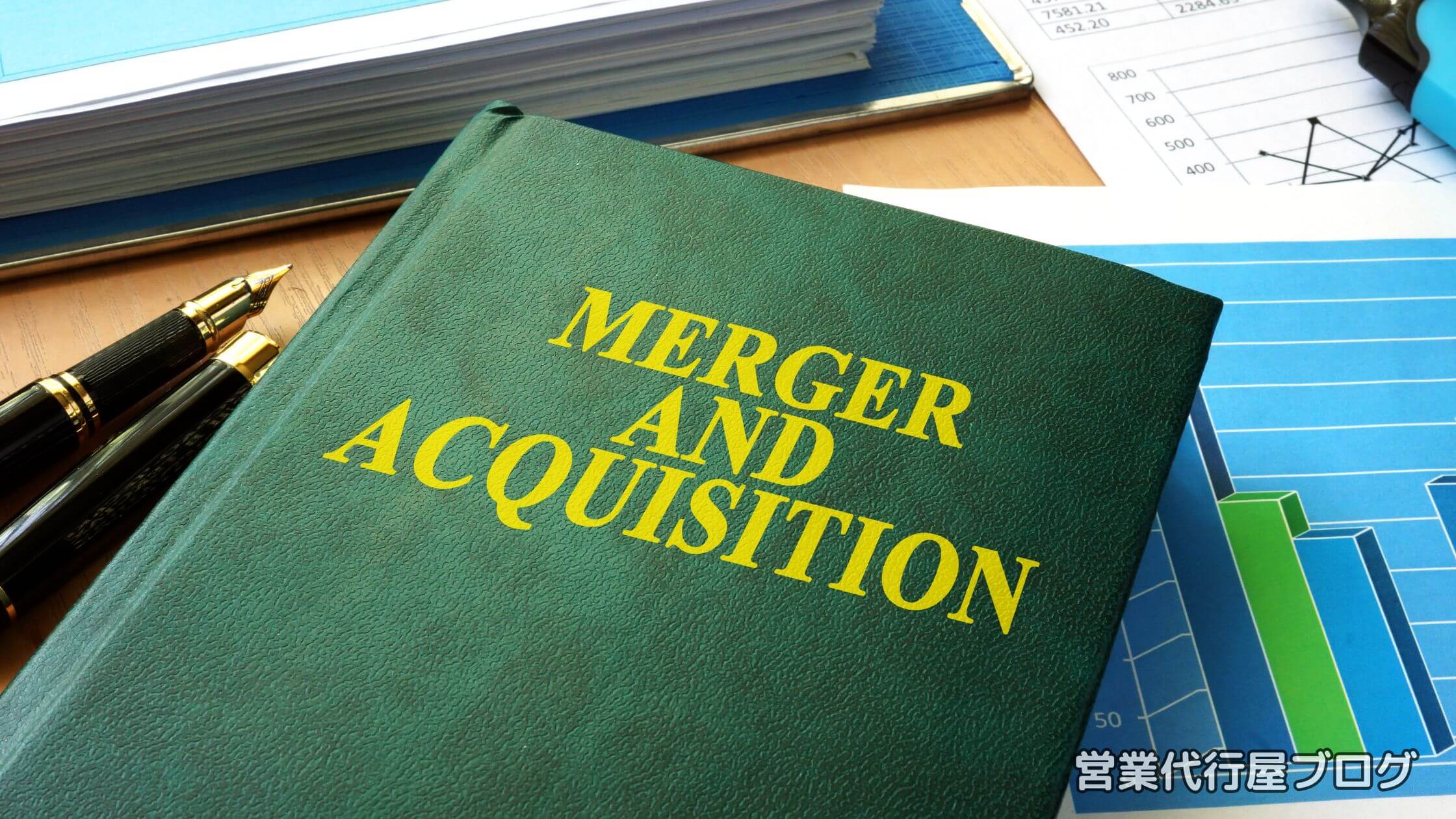









コメント